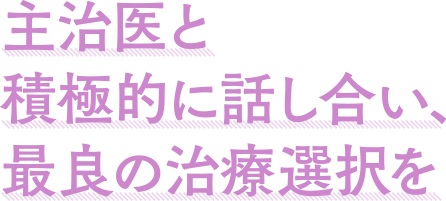先生からのメッセージ
先生からのメッセージ
- 新潟大学 保健管理センター 准教授
- 新潟大学医歯学総合病院 腎・膠原病内科

最適な治療法は患者さんによって異なる
患者さんにとって最適な治療法は、病状だけでなく、家庭環境、社会環境、経済状況、そして価値観など、様々な要因によって異なります。したがって、患者さんは「先生に任せる」のではなく、主治医と積極的に話し合い、一緒に治療法を決定していくことが望ましいです。そのためには、患者さんご自身が病気や治療について正しく理解する必要がありますが、インターネットなどで安易に入手した情報に振り回されることなく、信頼できる情報源に基づいて理解を深めていただき、また、疑問点があれば主治医に積極的に質問していただければと思います。
関節リウマチに合併しやすい骨粗鬆症
関節リウマチ患者さんは、骨粗鬆症を合併しやすく骨折リスクも高いことが知られています。その原因として関節リウマチによる炎症や骨吸収の亢進、痛みによる運動不足などが挙げられます。特に高齢者では骨粗鬆症の罹患率が高く、80代では2人に1人が骨粗鬆症であると言われています。また、閉経を迎えた女性は骨粗鬆症のリスクが急激に高くなるため、定期的に骨密度検査を受けていただきたいと思います。骨粗鬆症の予防には、牛乳や脂ののったお魚など、カルシウムやビタミンDを豊富に含む食品の摂取が効果的です。日光浴もビタミンDの生成を促すために良いでしょう。骨密度が低下した場合には、薬物療法が有効な手段となります。主治医と相談のうえ、適切な治療を受けることで骨粗鬆症の進行を抑制し、骨折のリスクを軽減することができます。

骨粗鬆症の予防にロコモーショントレーニング
骨粗鬆症の予防には、運動も欠かせません。徒歩など日常的な身体活動を増やすことはもちろん、筋トレで体幹を鍛えることやバランス力や柔軟性の向上に努めることも有用です。近年、ロコモティブシンドローム対策として、日本整形外科学会が推奨するロコモーショントレーニング(ロコトレ)が注目され、骨密度向上の効果も期待されています。ロコトレは、①片脚立ち(床につかない程度に交互に片脚をあげる)②スクワット(お尻を後ろに引くように、2〜3秒間かけてゆっくりと膝を曲げ、ゆっくり元に戻す)③ヒールレイズ(両足で立った状態でゆっくり踵の上げ下ろしをする)④フロントランジ(腰に両手をあて、両脚で立った状態から、片脚をゆっくりと大きく前に踏み出し、次に太ももが地面と平行になるまで腰を深く下げ、その後、身体を起こしながら踏み出した脚を元の位置に戻す)のほか、膝の痛み対策として⑤大腿四頭筋訓練(膝を伸ばして仰向けに寝て太ももに力をいれて脚を交互にゆっくり10cmほど上げる)があります。体力に不安がある方は、手を机や壁について体を支えたり、椅子に座って行うなど、無理のないようにしましょう。
骨粗鬆症が進行すると、上下方向からの圧力で背骨の特に前側がつぶれてしまう脊椎圧迫骨折が起こりやすくなります。これを防ぐためには、前かがみにならないよう背筋を伸ばし、正しい姿勢を心がけることが大切です。
高齢患者さんは朝からバランスよい食事を
高齢になると食事の摂取量が減り、痩せてしまう傾向があります。痩せると筋肉量が減少し、身体機能の低下につながりますので、どのようにして十分量の食事を摂るかが課題となります。適度な運動や香味野菜や酸味のある食材の活用は食欲増進に有効です。日本人は朝食は少なめに、昼食と夕食は多めに摂る傾向がありますが、筋肉を作る大事な栄養素であるたんぱく質は体内に蓄えることができないため、朝昼晩しっかり摂取することが望ましいです。さらに、高齢者は消化吸収や咀嚼の機能も低下するため、例えばお肉であればステーキよりもハンバーグにするなど食べやすくする工夫をしてください。

将来の妊娠・出産を見据えた「プレコンセプションケア」
若い女性患者さんでは妊娠や出産、子育てに不安を抱える方が多いです。しかし、疾患活動性をしっかりとコントロールすれば、出産も子育ても可能です。最近では、将来の妊娠・出産を見据えてパートナーとともに生活や健康に向き合う「プレコンセプションケア」が一般的になってきており、早い段階からパートナーと一緒に考えていくことが推奨されています。

佐藤 弘惠 先生
2001年新潟大学医学部医学科卒業。同年亀田総合病院臨床研修医。2003年新潟大学医歯学総合病院腎・膠原病内科医員。同年長岡赤十字病院内科医長。2004年新潟県立妙高病院内科医長。2007年新潟県立リウマチセンター内科医長。2008年新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻博士課程終了。2010年同大学医歯学総合病院腎・膠原病内科医員。2016年同大学保健管理センター講師。2022年より現職。
新潟大学医歯学総合病院
病床数:827床
所在地:新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地
※所属および掲載内容は、取材当時のものです。